こんにちは!実生mioです。
ここは、渡良瀬川と桐生川、ふたつの清流に抱かれた絹織物の町。
歴史ある里山🍃と、豊かな自然に囲まれた群馬県桐生市――
新緑や紅葉が美しい、四季折々の風景が楽しめる場所です。
床にもみじが映りこむ幻想的な秋の景色が魅力の【法徳寺】や、渡良瀬川の渓谷美と紅葉を一緒に楽しめる【高津戸峡】など、心も体もリフレッシュできる、寺と清流の癒し散歩コースをご紹介します。
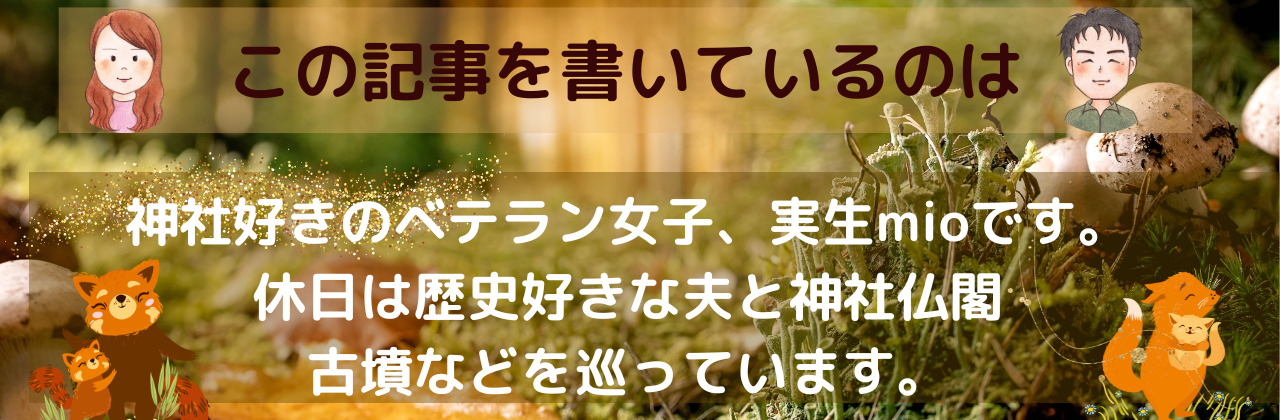
![]()
宝徳寺【秋の床もみじ】

2022年に訪れた宝徳寺の魅力と感想
五月、新緑のもみじが青くやわらかく風に揺れ、木陰には誇らしげに咲く牡丹の花。
足元には、どこか親しみを感じるコロンとしたお地蔵様。
境内には無数の風車がカラカラと音を立て、風に揺れる様子は、日々の煩わしさをそっと洗い流してくれるようでした。
十一月、赤城山からの冷たい風が吹きはじめ、もみじの葉を少しずつ赤く染めていきます。
この年は例年よりも暖かく、ゆっくりと色づく紅葉を長く楽しむことができました。
宝徳寺の魅力のひとつ御朱印
御住職の絵心が詰まった作品は、季節ごとに変化があり、お地蔵様や龍神の画など種類も豊富。
その筆が動く限り、御朱印の収集には終わりがありません。
中でも、床にもみじが映りこむ「床もみじ」は本当に見事で、庭園の小径は、写真を撮るために訪れる人がいるほど心地よい空間です。
拝観料は少々高め(1200円)ですが、その美しさを目にすれば、きっと納得の時間になることでしょう。
宝徳寺のお地蔵様

宝徳寺を訪れてまず目をひくのは、焼き物のような独特の色味をもつ石灯籠やお地蔵様たち。
その優しい表情に、ついカメラを向けたくなってしまう人も多いはず。

五月には青もみじと牡丹の花が風に揺れ、秋には赤城おろしがもみじを染めていきます。
例年より暖かかった2022年の秋は、紅葉の色づきもゆっくりで、長く楽しむことができました。

境内にはカラカラと回る無数の風車があり、まるで日々の煩悩を風がさらっていってくれるような心地よさがあります。
不思議なことに、お線香の香りはほとんど感じられず、お寺なのにどこか新鮮な印象。
宝徳寺の庭園

その理由のひとつが、芸術家でもあるご住職の感性。
伝統にとらわれすぎず、和の中に洋のセンスや遊び心が散りばめられた庭園は、限られた敷地の中に巧みに設計されています。

ハート型の砂紋は「三途の川」を表しているそうですが、きっとそこにはピンク色の優しい水が流れているのでしょう。
宝徳寺の床もみじ

特に、床にもみじが映り込む幻想的なお堂では、誰もが息をのむような美しい瞬間に出会えます。
水面のような床に映る紅葉は、まるで別世界。静かに、どこまでも深く、心の奥まで引き込まれていくようです。
高津戸狭散策コースの回り方

宝徳寺から車でおよそ5km。
桐生川の渓谷がつくり出すダイナミックな景観を楽しめるのが、ここ【高津戸狭(たかつどきょう)】です。
遊歩道を散策する前に、まず大事なのが歩く「ルート選び」。
おすすめは、上記地図の「P:はねたき広場」からスタートし、時計回りに歩くコース。
理由はシンプル、「下りが多くて楽」だからです♪
どちらの方向からでもアップダウンはありますが、階段の数や傾斜のきつさを比べると、断然時計回りの方が歩きやすく感じました。
はねたき道了尊

はね瀧道了尊
道了尊信仰は、ここ大間々独自の信仰の一つです。
その信仰は古く、250年以上も昔から続いており、地元民からは「どうりゅうさん」の呼び名で親しまれております。
はね瀧道了尊のお姿は、願主のもとに何よりも速く駆け付ける白狐の背に乗り、右手には、子どもの心に宿ろうとする悪鬼を懲らしめる為のねじり木を持っています。
道了尊信仰は、子どものねじれた性格を真っ直ぐに立ち直らせる事をその信仰の目的としています。子どもに対する親の想いがその信仰の中心となっています。
お参りの仕方は、親子で道了様を参拝し、ねじり木を一本持ち帰る。そのねじり木を家の清浄なる場所に祀り、朝夕ねじれた性格(非行)から立ち直ってもらいたいと念ずる。
その後道了様の霊験によりみごと立ち直った方は、お礼の参拝をする時、感謝の意を込め、ねじり木を二本にしてお供えします。
子どもがまっすぐに育ってほしいと思うのは、全ての親の願いです。その願いを聞き入れて下さる道了尊を、今一度お迎え致しました。また、道了尊の霊験は、開運、家内安全、交通安全等様々なお願いにも有効です。

はねたき橋と「道了尊さま」
コースの入り口・はねたき橋のたもとには、まるで門番のように佇む「はねた瀧道了尊(どうりょうそん)」の像が。
赤い大きな一本歯の下駄のそばに立つそのお姿は、天狗のような不動明王。
縄と棒を持ち、白狐にまたがる姿がなんとも印象的です。
全長120メートルのはねたき橋は歩行者専用で、谷底までの高さは……およそ100メートル!?
下をのぞき込むと思わず足がすくんでしまうほどのスリルがあります。
そのためか、かつては自殺の名所や心霊スポットともささやかれていましたが、私自身は何度訪れても不気味さを感じたことはなく、むしろ清らかで心がすっきりとするような散歩道です。
水の神様が、訪れる人々の苦しみをそっと受け取り、遠く海の底へと運んでくださるのかもしれません。

こちらの遊歩道(約500m)は短いながらも高低差が激しく、階段も多め。

妊婦さんやご高齢の方、足腰に不安がある方にはあまりおすすめできません。

上の画像の岩の人工的な部分は、昔のお城【高津戸城・1097~1104年】の名残りでしょうか?

◆甌穴(ポットホール)と渓谷美
はねたき橋を渡って進んでいくと、川岸に人だかりが見えてきます。
ここは、水流の力で岩が丸く削られた「甌穴(おうけつ)」が見られる珍しい場所。
「ポットホール」とも呼ばれ、まるで大きなかめのような丸い穴が点在しています。
その先に見えるのが、もう一つの赤い橋・高津戸橋です。
ここからは、はねたき橋と奥にそびえる赤城山を一望でき、まさに絶景!
高津戸ダム

さらに先へ進むと、小さなダム【高津戸ダム】へと続きます。
これは発電用の施設で、上流側の遊歩道を進んでから階段を下ってアクセスします。

高津戸橋

高津戸橋を渡ると見えてくるのが【ながめ公園】。
秋には「菊祭り」が開催され、多くの人で賑わいます(菊祭り期間中は入園料400円、普段は無料)。
ながめ公園

◆季節ごとの表情と眺めの名所「ながめ公園」
さらに進んでいくと、三つ巴の神紋が目印の「郷社 神明宮」もありますよ⛩️
「ながめ公園」の名前のとおり、この地から見下ろす高津戸狭の景色は、まさに息をのむほどの美しさ。
ぜひ、紅葉の時期に訪れてみてください。
大間々神明宮

郷社神明宮(大間々神明宮)基本情報
| 所在地 | 群馬県みどり市大間々町大間々2245 |
|---|---|
| 御祭神 | オオヒルメノミコト(天照大御神) トヨウケヒメノカミ |
| 御朱印受付 | 9~17時 |
| 御利益 | 五穀豊穣・産業復興・疫病退散 他 |
平成12年5月21日・国内産檜を用いて完成

なぜ高津戸峡に「神宮」?
郷社神明宮の由緒をたどって
高津戸峡の一角に「神宮」の名をもつ【郷社 神明宮】が鎮座していることに、ふと不思議を感じました。
伊勢神宮は三重県にあり、ここ群馬・桐生市からは500km以上も離れています。
その疑問に答えてくれたのが、境内にある由緒書きの案内板。そこにはこう記されていました。
「この地一帯は、かつて伊勢神宮の御厨(みくりや)もしくは“大蔵保(おおくらほ)”と呼ばれる領地だった可能性があり、田畑の痕跡が残っている。また、境内地からは縄文式・弥生式土器や、鉄の精錬に関わる“たたら製鉄”の鉱滓(こうさい)などが出土している。」
御厨とは、伊勢神宮に供物を納めるための直轄地のことで、全国各地に存在していました。
つまり、桐生にもかつて伊勢とつながる“神の台所”があったのです。
神社の創建は今から676年前の1347年(貞和3年)。
まず天照大御神を祀る社が建てられ、時を経て368年後には、伊勢神宮・外宮の主祭神「豊受大神」の分霊も勧請されました。
しかし、度重なる火災や大飢饉、終戦の混乱などもあり、神明宮の存続は決して容易ではなかったようです。
それでも、人々の信仰心は絶えず、鎮座650年・中興遷座400年の節目にあたる平成12年(2000年)に、崇敬者たちの寄進により現在の社殿が完成しました。
織物と水運のまち・桐生と伊勢のつながり
桐生の織物産業の歴史は平安時代までさかのぼります。
江戸時代には米や織物などを渡良瀬川の舟運で江戸へと運び、そこからさらに大阪方面へは海路で輸送が行われていました。
当時、陸路はコストも時間もかかるため、川や海の水運が物流の主力。
とはいえ、天候や川の水量次第で命に関わるリスクも伴う、厳しい仕事だったに違いありません。
桐生に残る「伊勢の御厨」の名残は、現代人の私たちには信じがたいほどの距離とつながりを持っています。
けれど、かつての人々の祈りと努力が、それを現実の形にしたのだと改めて感じます。
むすび

遥か昔、伊勢と桐生をつないだ信仰と暮らしの痕跡。
目には見えないけれど、風や水の流れに耳をすませば、今もなおその記憶がそっと語りかけてくれるようです。
実生mio



