こんにちは!実生です。
こちらでは、群馬県富岡市の妙義神社をご紹介いたします。
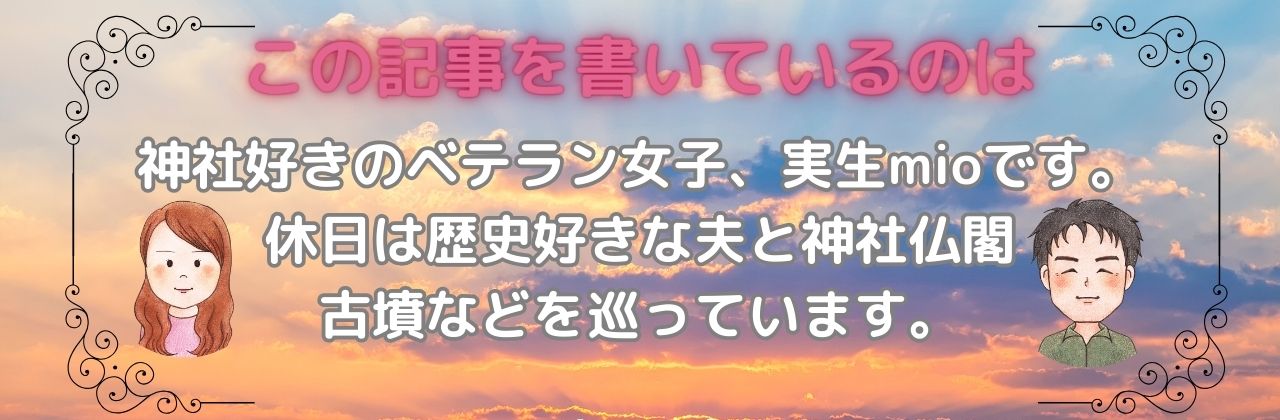
妙義山とは?日本三大奇景のひとつに数えられる霊峰
群馬県にそびえる妙義山(みょうぎさん)は、榛名山・赤城山とともに「上毛三山(じょうもうさんざん)」の一つに数えられ、さらに日本三大奇景のひとつとしても名高い山です。
「妙義山」という名称は、実はひとつの山を指すものではなく、白雲山・金洞山・金鶏山・相馬岳・御岳・丁須ノ頭・谷急山といった、複数の峰々を含めた総称です。
火山活動によって噴き出したマグマが地表近くで急冷されてできた安山岩で形作られた妙義山の姿は、切り立った岩肌や奇岩が織りなすそのダイナミックな造形から、**「奇景」「霊峰」**として古くから人々の信仰を集めてきました。
そのあまりの荘厳さに心を打たれたのが、御祭神のひと柱「権大納言 長親卿(ごんだいなごん ながちかきょう)」。
この山を「明魏(めいぎ)」と名付けたことが、後の「妙義(みょうぎ)」の名の由来となったと伝えられています。
🌸春の桜、🍁秋の紅葉、そして⛰圧倒的な岩峰の風景――
この山を見上げるだけで、何か大いなる存在に包まれるような気持ちになるはずです。
群馬県お花見スポット!妙義神社のしだれ桜

江戸の趣が息づく庭園と、四季折々の美しさ✨妙義神社の境内には、江戸時代の面影を色濃く残す建造物や広々とした庭園が広がり、どの季節に訪れてもその美しさに心を奪われます。
なかでも、🌸春のしだれ桜と🍂秋の紅葉は格別で、群馬県内でも屈指の人気を誇る花の名所・紅葉スポットとして知られています。
そして――
そよ風に揺れる「さくらの幣(ぬさ)」は、まるで訪れた人の心を静かに祓い清めてくれるよう。
この神聖で優雅な風景は、まさに春の妙義神社でしか味わえない特別な時間です。
🌸ああ、今年も来れてよかった──🌸
そんな思いが胸に広がる、春の妙義神社。
広大な境内はゆとりがあり、混雑を気にせずゆっくりと過ごせるのも嬉しいポイント。
富岡市の桜の名所、そして紅葉の名所として、毎年多くの人々を魅了しています。
しだれ桜のトンネルをくぐったその先には、
**1773年(安永2年)建立の「総門(そうもん)」**がひっそりと佇んでいます。
この総門は、もともと「白雲山石塔寺(はくうんざん せきとうじ)」の仁王門として使われていたもの。
現在では重要文化財に指定されており、時の流れと共に神社の歴史を今に伝えています。

歴史と桜が重なる風景──総門と石垣
総門が建つ石垣には、**「明和六年(1769年)」**の刻銘がしっかりと残されています。
この地で、250年以上の時を静かに見守ってきた証です。
ちなみにこの写真は、2023年4月1日に撮影したもの。
すでに一部の桜は散り始めており、桜の種類によって見頃に差があるのを実感しました。
「今年は咲くのが早い?遅い?」と悩みながらも、結局は毎年、満開も散り際も、それぞれの美しさがあるものですね。
とはいえ、ベストタイミングで訪れたい方は、やっぱり開花情報をチェックしてからのお出かけが安心です🌸📅




妙義神社の基本情報

紅葉も素晴らしい妙義神社の境内です。

| 住所 | 〒379-0201 富岡市妙義町妙義6 |
|---|---|
| 電話番号 | 0274-73-2119 |
| 公式サイト | https://www.myougi.jp |
| 御祭神 | 日本武尊(やまとたけるのみこと) 豊受大神(とようけのおおかみ) 菅原道真公(すがわらのみちざねこう) 権大納言長親興(ごんだいなごんながちかきょう) |
| 御利益 | 開運厄除け・商売繫盛・学業児童・農耕桑蚕・火防・縁結び・心願成就 |
| 拝観時間 | 9:00~17:00 |
妙義神社の神々

日本武尊(やまとたけるのみこと)
妙義神社の主祭神である**日本武尊(ヤマトタケル)は、古墳時代に実在したとされる皇族で、第12代・景行天皇の皇子。
本名は小碓命(おうすのみこと)**で、双子の兄・大碓命(おおうすのみこと)と共に生まれました。
その波乱に満ちた人生は、古代日本の神話や伝説に数多く語り継がれています。
倭国平定の伝説
兄を手にかけてしまったことで父・景行天皇との間に確執が生まれたヤマトタケルは、
豪族たちの反乱を鎮めるため、西国(九州)へと送り出されます。
熊曾建(くまそたける)兄弟との戦いでは、見事に勝利を収め、その強さを称えられて「タケル」の名を授かりました。
この後も「イズモタケル」との戦いに勝ち、出雲を平定。西国を制したヤマトタケルは大和に戻りますが、再び東征の命を受けることとなります。
東国平定と弟橘媛(おとたちばなひめ)
東征の途中、伊勢に立ち寄ったヤマトタケルは、叔母・倭姫命のもとで弟橘媛(おとたちばなひめ)と結ばれます。
2人は強く結ばれ、新婚旅行のように共に東国遠征へと向かいました。
神奈川・相模国では、草薙の剣で火を払い、火打石で向かい火を放ち、窮地を脱するという有名な「火中脱出伝説」が残されています。
さらに、走水(横須賀)から房総半島へ向かう航海では、海の神の怒りを鎮めるため、
弟橘媛が自ら海に身を投じるという悲しくも尊い犠牲が語られています。
群馬とのつながり
その後、ヤマトタケルは現在の**甲斐(山梨)⇒上野(群馬)⇒三峯(埼玉)⇒碓氷峠(長野)**と旅を続けました。
この東国平定の道中に群馬の地を通ったことが、妙義神社に祀られる由縁ともされています。
豊受大神(とようけのおおかみ)
五穀豊穣や食の神として有名で、伊勢神宮・外宮の御祭神でもあります。
農業守護や生活安定のご利益があるとされています。
菅原道真公(すがわらのみちざねこう)
学問の神様・天神様として全国で信仰される文徳の神。受験や学業成就を願う参拝者に篤く崇敬されています。
権大納言・長親卿(ごんだいなごん・ながちかきょう)
妙義山に感銘を受け、「明魏(みょうぎ)」と名付けた人物で、妙義神社の由緒とも深く関わっています。
その功績から神格化され、社の守護神として祀られています。
以上、妙義神社に祀られる神々のご紹介でした✨
ヤマトタケルの人生はまさに「命をかけた日本の旅路」──
その一部に群馬があり、妙義がある。それを感じながら訪れると、より一層深い祈りとなりそうですね🍃
妙義神社の境内は見どころ満載

見どころ満載!妙義神社の境内を歩く
総門をくぐった瞬間、目の前に広がるのは、とにかくスケールの大きな世界!
石段も社殿も灯籠も、すべてが堂々としていて、訪れる人の心をぐっとつかみます。
この荘厳な景観は、妙義山特有の硬く丈夫な地質があったからこそ実現できたもの。
人の手でつくりえた奇跡とも言える、まさに神域の風景です。
奉納された「変わり灯籠」にも注目!
妙義神社では、他ではあまり見かけない独特な形の灯籠がいくつも見られます。
これらは、当時の有力な商人や老舗など、社会的に影響力のあった人々によって奉納されたもの。
一基一基に名前が刻まれ、時代背景や信仰の深さを物語っています。
灯籠をひとつひとつ眺めながら歩くと、当時の人々の思いが静かに伝わってくるようです。
稲荷神社・和歌三神社

◇ 稲荷神社
五穀豊穣・商売繁盛のご利益で知られるお稲荷さま。
小さなお社ですが、朱色の鳥居とともに、境内に清らかな気を添えています。
◇ 和歌三神社(わかさんじんじゃ)
和歌や学問、芸能の神様をお祀りしている神社で、古くから文化を愛する人々に信仰されてきました。
学業成就や表現活動に携わる方にもおすすめです。
手水舎・授与所

重厚な存在感を放つ青銅の鳥居と灯籠

境内を歩いていると、ひときわ目を引くのが、青銅でできた鳥居と灯籠。
風雨にさらされてなお、その青みがかった重厚な色合いは、時を超えて静かに佇み続けています。
この鳥居と灯籠は、格式の高さや信仰の深さを象徴する存在とも言え、
神社の歴史と共に歩んできた重みが感じられる貴重な文化財です。
まさに「神域への入口」としてふさわしい風格。
その前に立つと、自然と背筋が伸び、神聖な空気に包まれる感覚を味わえるでしょう。

遥拝所(ようはいしょ)

銅鳥居の左側にひっそりと構える遥拝所(この位置から本社を遥拝できるのです)
妙義神社の境内には、山頂の奥宮を遥かに拝むことのできる**「遥拝所(ようはいしょ)」**があります。
険しい山道を登らずとも、山の神様に祈りを届けることができる場所として設けられたこの場所は、体力に自信のない方や、天候の悪い日にも安心してお参りができる“心の拠り所”です。
眼前に広がる妙義山を見上げながら、静かに手を合わせれば、まるで山そのものが神様の姿として語りかけてくれるような──
そんな、深い祈りとつながる時間を体験できる神聖なスポットです。

このようなお皿にお賽銭をし、拝みます。

銅鳥居や銅製の装飾が多い理由とは?
妙義神社の境内では、銅(青銅)で作られた鳥居や灯籠、装飾品が数多く見られます。
その重厚な輝きと風格は、時代を超えて神社の格式と歴史を物語っています。
では、なぜ銅がこれほど多く使われているのでしょうか?
それは、江戸時代の信仰の厚さと寄進文化に理由があります。
妙義神社は、江戸幕府の庇護を受けた名社として知られ、将軍家や有力商人、信仰篤い人々から多くの奉納があったとされています。
その中でも「銅」は、当時の富と信仰の象徴として特に価値ある素材でした。
また、銅は風雨に強く、長く美しさを保つことができるため、神聖な空間を守るにふさわしい素材として選ばれてきたのです。
重厚な青銅が放つ静かな存在感。
それは、信仰を形に残した人々の想いと、神域としての気高さが今もなお息づいている証かもしれません。
妙義神社の大杉

境内にそびえる大杉は、樹齢数百年とも言われるご神木。
その太く高い姿は、まさに神域の象徴です。
静かに手を合わせれば、大地の力とともに心が整っていくような不思議な感覚に包まれます。
波己曽社

妙義神社の境内にひっそりと佇む波己曽社は、古くから地元の人々に信仰されてきた小さなお社です。
農業の神や土地の守護神として祀られ、五穀豊穣・家内安全・厄除けなどのご利益があるとされています。
素朴で静かな雰囲気の中に、長く続く祈りの気配が感じられる場所です。
厳島社

妙義神社の境内にある厳島社は、**市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)**をお祀りする、美と芸能、水の神様の社です。
女性の守護神としても信仰され、容姿端麗・芸事の上達・良縁成就などにご利益があるとされています。
小さなお社ながら、やさしく清らかな気が漂うスポットです。
男坂・女坂・隋神門

妙義神社の本殿へ向かう参道には、2つのルートがあります。
ひとつは急勾配の石段が連なる**「男坂」、もうひとつは、やや、なだらかな「女坂」**。
どちらを選ぶかで、道中の印象も変わります。
坂を登りきると現れるのが、朱色が鮮やかな**「隋神門(ずいしんもん)」**。
神域への入口を守る門で、ここから先は特に清らかな気が漂うエリアです。
体力や気分に合わせて坂を選び、静かに隋神門をくぐるひとときは、まさに心身を整える小さな“禊”のよう。
本社・唐門

妙義神社の本社は、江戸時代・宝暦年間に再建された重厚な社殿で、彫刻や装飾が非常に華やか。
随神門をくぐり石段を上った先に、その堂々たる姿が現れます。
本社へと続く**唐門(からもん)**は、曲線が美しい屋根と精巧な細工が特徴の歴史的な門で、まさに“神域の中心”へ足を踏み入れるための特別な入口。
その造りや意匠から、当時の職人たちの技と信仰の深さが感じられる、見どころのひとつです。

石段の上にある唐門は、赤と金の装飾×紅葉でまるで異世界です✨
水神社(みずじんじゃ)

妙義神社の境内にひっそりと鎮座する水神社は、水の神様をお祀りする小さなお社です。
生活に欠かせない清らかな水を守る存在として、雨乞いや水難除け、五穀豊穣などのご利益があると伝えられています。
木々に囲まれた静かな場所にあり、心がすっと落ち着く癒しのスポットです。
影向石

妙義神社の境内にある**影向石(ようごうせき)**は、神様がこの地に現れる際に降り立つとされる神聖な石です。
昔から「神が宿る場所」として大切にされ、今も多くの参拝者が静かに手を合わせるスポット。
石の前に立つと、どこか空気が変わるような、神様の気配を感じる特別な場所です。
人も少なくて、静かに秋の神さまとおしゃべりできた気分☺️🍂

🍁群馬・妙義神社の紅葉
険しい妙義山の岩肌に、静かに燃えるような紅葉。
歴史ある社殿と、色づいた木々が織りなす風景は、心がすっと澄んでいくようでした。

紅葉の盛りは11月上旬〜中旬。
混雑も少なく、ゆったりと歩ける穴場です。
時の流れにふと立ち止まりたくなったら、こんな秋の神社旅もおすすめです。

旧宮様御殿(きゅうみやさまごてん)

旧宮様御殿は、かつて皇族(宮家)の方が参拝時に使用された御殿で、
その格式の高さから、妙義神社の特別な歴史を今に伝える貴重な建物です。
現在は一般には立ち入れませんが、外観からもその風格と静謐さが感じられます。
境内を訪れた際には、ぜひそのたたずまいにも注目してみてください。

妙義神社では、日本の礎を築いた偉人・聖徳皇太子もお祀りされています。
十七条の憲法を制定し、仏教の興隆に尽くしたことで知られる太子は、調和・知恵・慈悲の象徴として広く信仰されています。
その徳を敬い、太子像や御神影に手を合わせる人も多く、
今なお人々の心を導く存在として境内に静かに祀られています。
天空の神社──妙義神社まとめ

群馬県・上毛三山に数えられる妙義山のふもとに鎮座する、壮大な自然と信仰が息づくパワースポット🍃✨
山肌に抱かれるように建つ妙義神社は、まさに**“天空の神社”**。
急勾配の石段を登ったその先に広がるのは、空と山、そして神が交わるような神秘の空間。
見下ろせば雲海、見上げれば青空──まるで天と地の境目に立っているかのようです。ここに立つだけで、日常の悩みがふわりと軽くなるような、不思議な解放感に包まれます。
標高約540メートル。✨天空の神社に、心を澄ませて✨
空に近い神域で手を合わせると、日常では得られない静けさと解放感に包まれます。
自然、神話、歴史、信仰──すべてが一体となったこの神社で、自分自身と向き合うかけがえのないひとときを、ぜひ体験してみてください。




