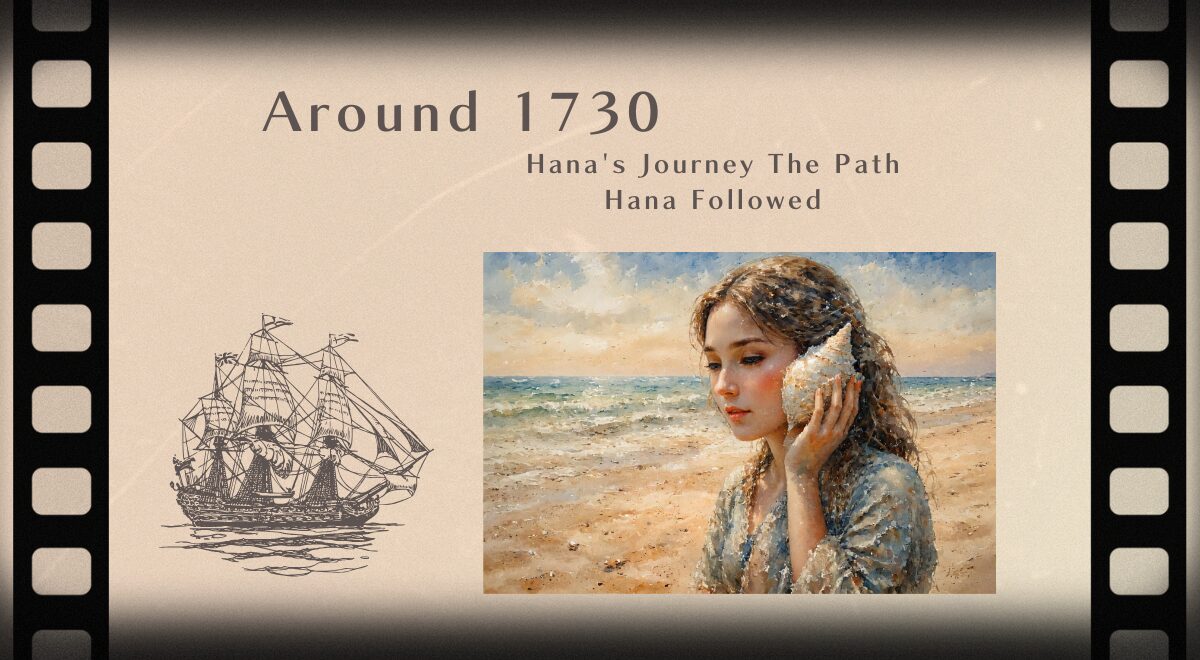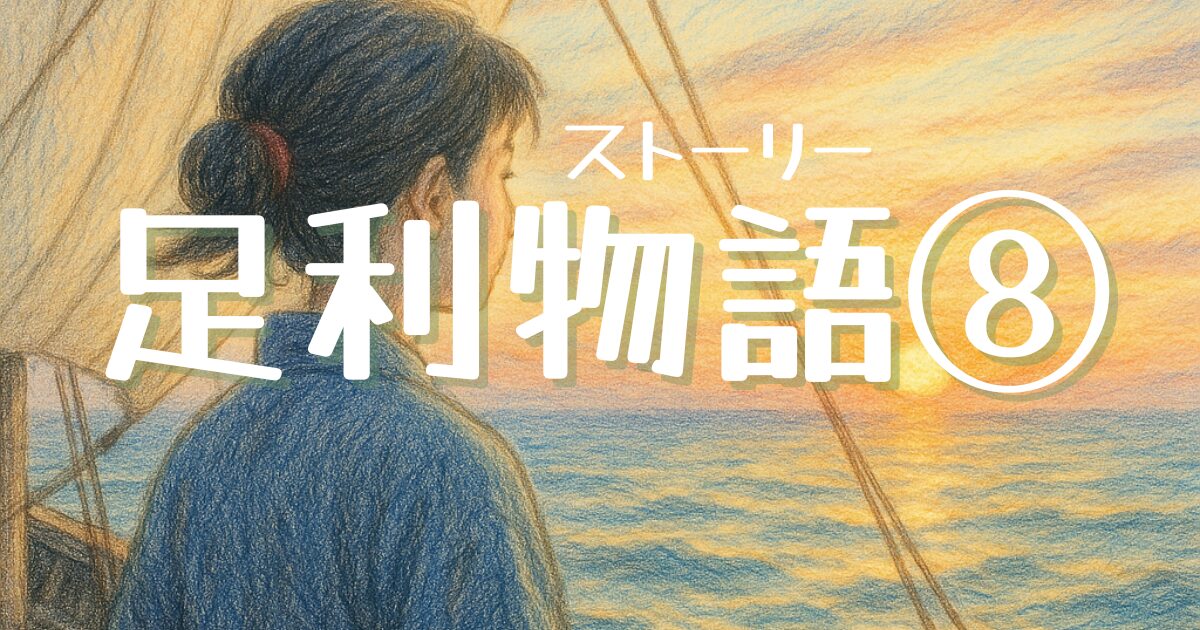伊勢からの帰省・江戸時代の海路
伊勢での日々は、思いがけず心地よいものだった。町の人々にも打ち解け、奉公の仕事にも慣れ、ここで暮らしていくのも悪くない――そう思い始めた矢先のこと。
足利の女将からの荷の中に、一通の手紙と費用が忍ばされていた。
けれど、その荷が伊勢に届くまでには危うい事情があったという。中山道は長雨でがけ崩れが起こり、渡し場の川も氾濫して、荷馬車が足止めを食っていたのだ。
「よくぞ無事にここまで運ばれたものだ」――呉服屋の主人はそう首を振った。
封を切ると、女将の筆が目に飛び込む。墨跡鮮やかな文にはこうあった。
「そろそろ足利へ戻る頃合いと考え、江戸へ向かう廻船にお前を乗せられるよう取り計らいました。費用も添えますので、安心して道中をおゆきなさい」
ハナは手紙を握りしめ、胸が熱くなった。もし荷が届かなければ、このまま伊勢に残っていたのかもしれない――そう思うと、今ここに手紙を受け取れたことが不思議な巡り合わせに思えた。
思えば何度も眺めたあの港の舟に、自分が乗る日が来るとは夢にも思わなかった。
伊勢の呉服屋の女将からは、旅に備えて軽く動きやすい作務衣を手渡される。布のやわらかさと匂いに、ほんの少し心が落ち着いた。
「帰るんだ……」
楽しかった伊勢の日々を胸に抱きしめ、ハナは白帆のそびえる港へと歩みを進めた。
出帆と風待ち
鳥羽の港には、白い帆をたたんだ大きな廻船がずらりと並んでいた。
空に高く伸びる帆柱は、風を待つ巨人のようで、港全体が静かに息をひそめているように見えた。
「船は風次第だからな」
足利から荷を運んできたおじさんが、にこにこと笑いながら言った。
彼も江戸まで荷を届けるため、この船に乗り込むという。
不安でいっぱいのハナも、その言葉に少しだけ肩の力が抜けた。
しかしその日は凪。
船頭が「今日は動けねえぞ!」と叫ぶと、旅人たちの間からため息が広がった。
茶屋の軒先では、魚を焼く煙が潮の風にのって漂い、旅人たちは熱い茶をすするしかなかった。
船宿の畳にはぐったり横になる人々。子どもを連れた母親が退屈しのぎに歌を口ずさむ。
「風が変わらなきゃ一歩も動けない」――それがこの海の掟なのだ。
船出
数日が過ぎ、ついに港にざわめきが走った。
「風が変わったぞ!」という船頭の声。
長らく眠っていた帆がぐぐっと持ち上げられ、布が大きくふくらんで「ばさっ!」と鳴り響いた。
港の人々が一斉に顔を上げる。
縄が外されると、船体がぎしりと揺れ、ゆっくりと水を切って進み出した。
足もとがふわりと浮くようで、ハナは思わず両手で作務衣の袖を握りしめた。
怖さとわくわくが入り混じり、胸がどきんと高鳴る。
「大丈夫だよ、足利までちゃんと行けるっしょ!」
横でおじさんがやさしく笑う。
その言葉に、潮風の冷たさが少しだけ和らいだ気がした。
おじさんはふと港の方を振り返り、声を落として言った。
「そういえば、お前さんの奉公先と縁のある柏崎家のことを知っとるんか?」
ハナは驚いて顔を向ける。
「柏崎家はな、ひと頃“年貢をごまかした”なんて濡れ衣を着せられて、危うく取り潰されるとこだったんだ。
けどな、小作人たちが口を揃えて『あの家のおかげで生きてこられた』って証言したんだと。
そのおかげで真実が明らかになって、今でも義理堅い家だって評判なんだ」
潮風に混じって、おじさんの言葉が重みを持って胸に響く。
ハナは足利で出会ったヤエの顔を思い浮かべた。
越後の大地と、今自分がいる伊勢の海とが、不思議と一本の線でつながっていくような気がした。
寄港 ― 御前崎にて
船は伊勢湾を抜け、熊野灘を越え、やがて遠州灘へと入っていった。
伊勢を出たときは海はまだおだやかで、港や村の灯りが遠くに見え、人の声さえ届くような気がした。
けれど紀州の沖にさしかかると、海は急に顔を変えた。
波が持ち上げてはどんと落とし、胸がひやりとする。
「ここからが本当の海だ」
おじさんの声に、ハナは唇をかんで帆柱を見上げた。広い海は波が荒く、帆が強く揺れるたびにハナの心臓もどきんと跳ねる。
ようやく船が御前崎の港に入ったとき、胸の底から安堵の息がこぼれた。
港にはすでに何艘もの船が並び、帆をたたんで風を待っていた。
船宿の前には旅人や船乗りたちが腰を下ろし、浜辺では子どもたちが魚を干している。
潮の匂いに混じって、焼いた小魚の香りが漂ってきた。
「ここでしばらく風待ちだな」
荷馬車のおじさんがそう言って、茶店の軒先に腰を下ろす。
旅人たちは茶をすすり、誰もが空を見上げては風の変化を気にしていた。
港町でのひととき
ハナは茶をすするおじさんの横で、荷を積み下ろす人々の姿を眺めていた。
大きな酒樽、反物の包み、塩や干魚の俵――。
荷のひとつひとつに、誰かの暮らしや生きる糧が詰まっているように思えた。
「商いって、こんな流れになっているのか……」と、ハナは心の中でつぶやいた。
足利から伊勢へ、伊勢から江戸へ、そして江戸からまた各地へ。
船はただの乗り物ではなく、人の縁や暮らしそのものをつないでいるのだと、ハナは少しずつ感じはじめていた。
船内:保存食が中心(干魚・味噌玉・梅干し・干し飯=お湯で戻すご飯)。寄港地:茶屋で焼き魚や団子、味噌汁などを食べられた。船宿では**温かい食事(煮物・飯・味噌汁)**が出て、旅人にとって大ごちそう。
船内:基本は床板に筵(むしろ)や敷物を敷いて雑魚寝。
船宿:港での風待ち中は船宿に泊まる。畳敷きの大部屋に数人ずつ。男女で区切られることもあったけど、基本は簡素。女性旅人がいる場合は、仕切りや家族同伴で寝泊まりすることが多かった。
江戸時代の「菱垣廻船」「樽廻船」などの大きな船:20〜30人前後の船頭・水夫が乗務。旅人は定員ではなく“荷のついで”で乗せてもらう → 数人〜十数人。
大名行列の移動ならもっと多く乗ることも。
ハナの場合は「荷物が主、旅人は少数の相乗り」のイメージ。
港町での冒険
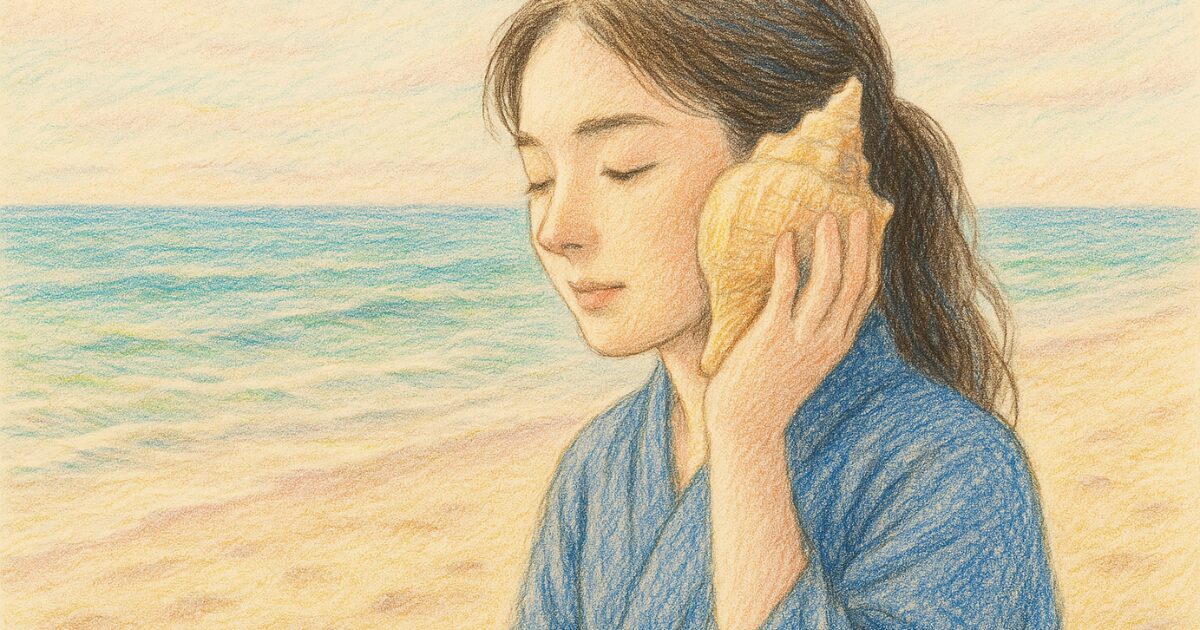
船宿に荷を置いたハナは、じっとしていられず港を歩いた。
海辺には小さな祠があり、漁師たちが旅の無事を祈って手を合わせていた。
「海の神さまに願っておくといい」
おじさんの言葉にうなずき、ハナもそっと手を合わせる。潮風にさらされた鳥居は苔むし、ずっと昔からここで船を見守ってきたようだった。
港町を歩いていると、子どもたちが砂浜にござを広げて、色とりどりの貝殻を並べていた。
ハナは思わず立ち止まる。白く透きとおったもの、赤く縁どりされたもの、小さな螺旋を描いたもの。
「お嬢さん、この白いのは耳に当てると海の音がするんだよ」
いたずらっぽく笑う子どもにすすめられ、ハナは手に取って耳に当ててみた。
……ざざん、と、潮騒のような響きがした気がした。
「これはヤエにあげたい」
海を見たことのないあの子が、この音を聞いたら、きっと目を輝かせるに違いない。
ハナは小さな銭を払って、白い貝殻を大事に包んだ。
さらに歩くと、市場の片隅に“外国から流れ着いた品”と書かれた木札が立っていた。
打ち寄せられた流木や、壺のかけら、見たこともない形の陶片。
その中に、光をはじく丸いガラス玉がひとつ、陽の光を受けて青く輝いていた。
「南の方の国から流れてきたらしいよ」と茶店の女将が教えてくれる。
ハナは手に取った。冷たくて、吸い込まれるような青。
「これはキヌに」
布を織る彼女が見たら、きっと「海の色みたいだね」と微笑むだろう。
ハナは胸が高鳴り、銭袋から少し大きな銭を取り出した。
小さな荷物が二つ、懐にしまわれた。
白い貝殻と青いガラス玉。
ほんのわずかな品なのに、仲間の笑顔が鮮やかに浮かび、海辺の港町がもっと身近に感じられた。
外洋と富士山
海に出ると、陸とはまるで違った。
船はゆらゆらと大きく揺れて、床に置いてあった桶の水がこぼれ、裾まで濡れてしまった。
まっすぐ立つのもむずかしくて、ヤエは柱につかまりながら空を見た。
そのとき、雲の切れ間から大きな山があらわれた。
白い雪をいただいて、海のむこうにぽつんと浮かんでいるように見えた。
「富士山だ……」
声に出すと、胸がじんとした。
足利からも見えたことがあるあの山と、今ここで出会えるなんて。
遠いのに、不思議と近くにいる気がした。
船はまだ揺れていたけれど、富士の姿を見ていると少し落ち着いた。
まるで大きな山が「だいじょうぶ」と言ってくれているようだった。
🔍 ちょこっと解説:海の違い(イメージ)
御前崎の港内や湾内
波は比較的おだやかで船も港に守られて揺れが小さい
潮風は湿っているけど、まだ「町の匂い」と混じって安心感あり外洋(遠州灘や駿河湾)
波が大きく、船が上下に大きく揺れる横風が強く、帆がばさばさ鳴って軋む
風が冷たく乾いて、潮の匂いが強烈に感じられる陸が見えなくなる瞬間があって、不安が増す
夜の海と星空
夜の海はどこまでも黒く、波と風の音しか聞こえなかった。
船が進んでいるのか、ただ流されているのかもわからない。
ハナは懐から小さな御守りを取り出した。
伊勢のおかげ参りのときに授かったものだ。
「ここに神さまはいる」――そう思うだけで、胸がじんと温かくなる。
ぎゅっと握ると、布に包まれた木の珠が手の中でかすかに震えた気がした。
怖さを越えたその先には、もう受け入れるしかなかった。
…
船が揺れるたびに体を合わせ、波にゆだねる。
すーっと、全身の力をぬく。
もう抗わない。
すると、さっきまでの恐ろしい揺れが、子守唄のように思えてくる。
船と一体になって、ただ大きな海に漂う自分。
その瞬間、空がふっと広がった。
見上げれば、数えきれないほどの星。
海と空の境目が消えて、船は星の川の中を進んでいるように見えた。
「こんなに星があったんだ……」
小さな声がこぼれる。
星々の光が冷たい風をやわらげ、御守りの温もりと重なって胸の奥を満たす。
怖さはもうなかった。
ただ大きな世界の一部として、船も自分も星と同じように漂っている。
その不思議な静けさに包まれながら、ハナはいつのまにか目を閉じていた。
おかげ参り(江戸時代の伊勢参詣)は数十万人規模で行われ、御守りは「家族の分まで持ち帰る」ほど大事にされた。
ハナ、江戸から足利へ
江戸の港は、人と船であふれていた。
白い帆が立ち並び、魚の匂いと掛け声が渦を巻いている。
伊勢を出てからの日々が胸によみがえり、ハナは思わず息をのんだ。
――ここが江戸。
けれど、まだ旅は終わりではない。
ここから舟を乗り継ぎ、渡良瀬川をさかのぼって足利へ戻らなければならなかった。
海の荒さとは違い、川の流れは静かだった。
舟は馬や人に引かれてゆっくり進み、両岸には田畑や小さな村が続く。
夕暮れには野に泊まり、朝にはまた櫂の音とともに川を上った。
二週間ものゆるやかな旅の間、ハナは何度も夜の海と星空、そして夜明けの光を思い出していた。
やがて舟は猿田(ヤエンダ)河岸に着いた。
川べりには荷を積み下ろす人でにぎわい、問屋ののぼりが風に揺れていた。
「ここからが足利だ」
おじさんの声に、胸の奥がじんわりと熱くなる。
伊勢からの長い旅が、ようやく一つの終わりを迎えたのだった。