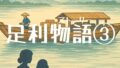江戸時代半ば、足利と伊勢をつなぐ道

徳川吉宗の倹約令が出された世の中、庶民の暮らしは少しずつ豊かさを増していた。
町には寺子屋が増え、人々は文字を学び、旅や信仰に心を向けるようになっていた。
伊勢神宮へのおかげ参りも、この頃になると大ブームになっていた。
そんな時代、足利の御厨神社は伊勢神宮に供物を納める拠点とされていた。
足利で織られた絹は、この神社から祈りを添えて伊勢へと運ばれていったという。
絹と祈り、御厨神社の春

御厨神社の境内には、絹反物を積んだ荷馬車が並んでいた。
織り手の娘たち、商人たちが集まり、神主が祝詞を唱えると、その場にいた人たちは静かに頭を下げた。
桑畑の若葉を揺らす春風の中、遠くで八木節の調子が聞こえ、人々の表情がふっとやわらいだ。
ハナ、伊勢に着く

「女将さん!わたしを伊勢に行かせてください!」
ハナは奉公先の女将さんに頭を下げた。
女将さんは目を丸くして笑った。
「伊勢? あんた、どこまで好奇心が強いんだい」
「お伊勢さまは一生に一度はお参りした方がいいって聞きました。
それに、女将さんの故郷でしょう? 案内を頼りに行ってみたいんです」
女将さんはしばらく考え込んだが、やがてため息をついてうなずいた。
「そうかい…。じゃあ、この店の反物を持って行っておいで。
伊勢で売れれば、旅費くらいにはなるだろう」
「ありがとうございます!」
こうしてハナは反物を荷に積み、中山道を目指すことになった。
道中は長い。
宿場町をいくつも越え、見知らぬ土地で一夜を明かすこともあるだろう。
帰りがいつになるかは誰にもわからない――。
この時、ハナ自身もまだ知らなかった。
旅の帰り道が、想像以上に遠く、長い道のりになることを。
長い旅の末、荷馬車はついに伊勢にたどり着いた。
街道はおかげ参りの人々でにぎわい、
「お伊勢さんだよ!」「よう来なすった!」と声が飛び交っている。
宿屋や土産物屋、赤福のような甘味を売る屋台まで並び、まるで祭りのような賑わいだった。
ハナは思わず立ち止まり、きょろきょろと辺りを見渡す。
「ここが……お伊勢さん……」
目の前に広がるのは、これまで見たことのない大きな鳥居と参道。
白装束の参拝者や子ども連れの家族も行き交い、空気が特別に澄んでいる気がした。
荷馬車を引いていた商人のおじさんが笑った。
「どうだい、ハナ。足利の町とはずいぶん違うだろう?」
「うん……空気が違う。なんか、すごい……」
胸いっぱいに深呼吸すると、伊勢の森の清らかな匂いがした。
奉納の絹反物は神宮の御用所へと届けられ、神職の人々が静かに受け取っていった。
その様子を見ながら、ハナはこっそり祈った。
「足利の絹が、神様の御衣になりますように……」
その夜、宿屋の縁側で星を見上げたハナは、ふと足利の仲間たちの顔を思い出した。
この旅を終えたら、もっといろんな場所を見てみたい。
そんな新しい夢が、胸の中に芽生えていた。
現代に残る足利御厨神社
今も足利には御厨神社があり、その歴史を静かに伝えている。
当時のように伊勢へ絹を運ぶことはなくなったけれど、足利の織物文化は今もこの町を彩っている。
旅立ったハナのように、足利の人たちは昔も今も、新しい世界へ一歩踏み出す気持ちを忘れていないのかもしれない。