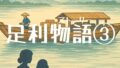奉公で暮らすキヌの一日
そのころ足利では、ヤエもハナも旅に出たまま、家は少し静かになっていた。
町の通りは朝からにぎやかだ。
旅籠(はたご)では旅人が朝げをとり、馬子(まご)が荷を積み直す。
日光例幣使街道を行き交う人の声と、渡良瀬川の舟の掛け声が交じり合い、
宿場町らしい忙しさを見せていた。
町の外れには桑畑が広がっている。
養蚕のために植えられた桑は、絹糸を生む命の糧だ。
反物を織るための糸は、この桑の葉で育った蚕から生まれる。
足利は昔から絹織物の町として栄え、町中には染め屋や織屋が並んでいた。
町には水路が通され、荷物や染め物を運ぶのに使われていた。
ときには家屋の中にも水が引かれ、川の水を利用して生活や仕事をしていた。
「この町は水に生かされているな」と誰かが言う。
だが同時に、渡良瀬川は暴れ川で、洪水の記憶も絶えない。
水は恵みであると同時に、恐ろしいものでもあった。
織女キヌの日常
そんな町で、キヌは奉公仲間と肩を並べて機(はた)を踏む。
新潟から奉公に来てもう一年。最初は指を切り、足がつって泣いた夜もあったが、
今では一日中織り続けることが当たり前になっていた。
織り上げた反物の一部は町の小さな祠に奉納する。
織物の神様に感謝し、家族の無事を祈る。
祠に手を合わせるたび、キヌは遠く離れた新潟の家族を思い出す。
雪国の田んぼ、囲炉裏を囲んだ温かい食卓…。
「みんな、元気にしてるかな」
そんな想いを胸に、翌日もまた機を踏む。
足利の夕げ
夕方になると、町は味噌汁の香りに包まれた。
奉公仲間3人で囲む食卓に、今夜は女将さんも顔を出した。
麦飯と野菜の味噌汁、漬物。
今日は川でとれた小さな鮎も焼かれている。
女将さんは膝をつきながら笑った。
「ヤエはうまくやっているかしらねえ、江戸で」
「きっと大丈夫ですよ、女将さん」
仲間のひとりが答えると、キヌもうなずいた。
「だって、ヤエは帳面付けも得意ですもの」
その言葉に女将さんは微笑み、
「そうだねえ、あの子はしっかり者だもの」とつぶやいた。
質素だけれど、笑い声の絶えない時間。
遠い江戸で頑張っているヤエのことを思いながら、
足利の夕げは静かに、そして温かく続いていった。
江戸へつながる足利
夜になると、荷を背負った商人がヤエンダ河岸へと急ぐ。
舟は今夜も江戸へ向かって滑り出した。
足利の織物は、川と道を通じて遠くまで運ばれていく。
その一端を担うキヌの仕事もまた、この町を支えていた。
江戸時代の宿場町で重要な役割を果たした宿泊施設を指す言葉。
馬子(まご)
馬を使って人や物資を運ぶことを業とするもの。